News
UTEC NEWS
2024年11月8日(金)、日本橋ライフサイエンスハブにて、「Science2Startup Japan Final Symposium 2024」が開催され、国内外から200名以上の業界関係者が参加しました。

Science2Startup(S2S)は、2018年にボストンを拠点とする投資家によって立ち上げられたグローバルプログラムであり、アカデミア発の技術シーズを基盤とするスタートアップを通じて、医薬品やライフサイエンス分野の開発に貢献することを目指しています。このプログラムは、世界各地の研究者に対して、スタートアップ設立や事業展開のためのノウハウを共有する社会貢献活動として位置付けられており、これまでに多くの研究者が参加し、経営者や投資家とのネットワークを構築する場として大きな役割を果たしてきました。これまでに13社以上のスタートアップが、このプログラムを通じて誕生しています。
Science2Startup Japan(S2S Japan)は、発起人であるS2S本部、AN Venturesと連携して、日本のライフサイエンス分野における最先端の技術シーズを支援するため、LINK-J、CIC、delight venturesに加えてUTECも運営に入る形で、2024年に設立されました。本プログラムは、ライフサイエンス領域で革新的な研究を行う日本の研究者が、グローバル投資家の協力を得ながら、技術シーズを医薬品開発やライフサイエンス産業への応用に向けた事業プランに磨きをかける機会を提供しています。
今回のシンポジウムは、S2S Japanでの第1回事業シーズ公募に申請いただいた多数の研究者らの中からファイナリストに選ばれた、岡山大学の中山雅敬氏、国立循環器病研究センターの中岡良和氏、鹿児島大学の中谷智子氏、名古屋大学の阿部洋氏、順天堂大学の松本征仁氏、理化学研究所の小泉智信氏の6名が事業化プランを最終発表する場として開催されました。
米国VCでメンターを務めたRA Capital ManagementのAndrew Levin氏、RA Capital ManagementのJosh Resnick氏、Insight PartnersのAiden Aceves氏、DCVC BioのEric Shiozaki氏、Arch Venture PartnersのAri Nowacek氏が来日の上、S2S Japanに参加しました。日本側でメンターを務めたUTECの塩原梓がモデレーターを務め、中岡良和氏とその米国側メンターのAndrew Levin氏 、中谷智子氏とその米国側メンターのAiden Aceves氏に、各々、本プログラムで得た経験や今後の事業化への期待についてインタビューを行いました。

パネルディスカッションでは、厚生労働省 医薬産業振興・医療情報企画課長の水谷忠由氏、経済産業省 生物化学産業課長の下田裕和氏、内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 参事官補佐の伊藤匠氏が登壇し、UTECの宇佐美篤がモデレーターを務め、日本のライフサイエンスエコシステムのグローバル展開について議論が交わされました。

その他にも、ジョンズ・ホプキンス大学のPaul Rothman氏からアカデミアに起業家精神を根付かせるための取り組みについて、スポンサーのCooley法律事務所のJosh Seidenfeld氏とEYのPhil Howard氏から米国で起業するための法務・財務について、CruxioのRob Wishnowsky氏から効果的なコミュニケーション等について、講演が行われました。
イベント終了後にはネットワーキングレセプションが開催され、参加者が交流を深め、情報交換を行う場が設けられました。
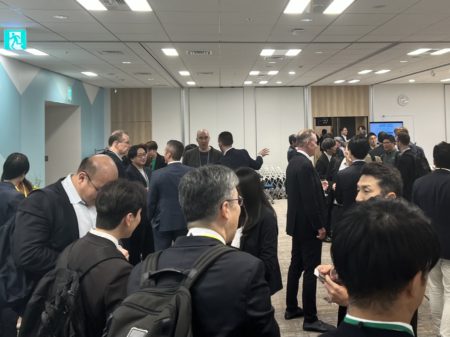
Science2Startup Japan Final Symposium 2024は、日本のアカデミア発のライフサイエンス技術シーズを医薬品産業に応用するための革新的なステップとなりました。
UTECとしても、S2S Japanを通じて、日本の研究者とグローバルパートナーが共に未来を創出する場を提供することで、日本のライフサイエンス分野が国際社会で飛躍する一助となれるよう、今後も取り組んでまいります。

Science2Startup(S2S)は、2018年にボストンを拠点とする投資家によって立ち上げられたグローバルプログラムであり、アカデミア発の技術シーズを基盤とするスタートアップを通じて、医薬品やライフサイエンス分野の開発に貢献することを目指しています。このプログラムは、世界各地の研究者に対して、スタートアップ設立や事業展開のためのノウハウを共有する社会貢献活動として位置付けられており、これまでに多くの研究者が参加し、経営者や投資家とのネットワークを構築する場として大きな役割を果たしてきました。これまでに13社以上のスタートアップが、このプログラムを通じて誕生しています。
Science2Startup Japan(S2S Japan)は、発起人であるS2S本部、AN Venturesと連携して、日本のライフサイエンス分野における最先端の技術シーズを支援するため、LINK-J、CIC、delight venturesに加えてUTECも運営に入る形で、2024年に設立されました。本プログラムは、ライフサイエンス領域で革新的な研究を行う日本の研究者が、グローバル投資家の協力を得ながら、技術シーズを医薬品開発やライフサイエンス産業への応用に向けた事業プランに磨きをかける機会を提供しています。
今回のシンポジウムは、S2S Japanでの第1回事業シーズ公募に申請いただいた多数の研究者らの中からファイナリストに選ばれた、岡山大学の中山雅敬氏、国立循環器病研究センターの中岡良和氏、鹿児島大学の中谷智子氏、名古屋大学の阿部洋氏、順天堂大学の松本征仁氏、理化学研究所の小泉智信氏の6名が事業化プランを最終発表する場として開催されました。
米国VCでメンターを務めたRA Capital ManagementのAndrew Levin氏、RA Capital ManagementのJosh Resnick氏、Insight PartnersのAiden Aceves氏、DCVC BioのEric Shiozaki氏、Arch Venture PartnersのAri Nowacek氏が来日の上、S2S Japanに参加しました。日本側でメンターを務めたUTECの塩原梓がモデレーターを務め、中岡良和氏とその米国側メンターのAndrew Levin氏 、中谷智子氏とその米国側メンターのAiden Aceves氏に、各々、本プログラムで得た経験や今後の事業化への期待についてインタビューを行いました。

鹿児島大学 中谷智子氏、Insight PartnersのAiden Aceves氏、UTEC 塩原梓
パネルディスカッションでは、厚生労働省 医薬産業振興・医療情報企画課長の水谷忠由氏、経済産業省 生物化学産業課長の下田裕和氏、内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 参事官補佐の伊藤匠氏が登壇し、UTECの宇佐美篤がモデレーターを務め、日本のライフサイエンスエコシステムのグローバル展開について議論が交わされました。

経済産業省 下田裕和氏、厚生労働省 水谷忠由氏、内閣府 伊藤匠氏、UTEC 宇佐美篤
その他にも、ジョンズ・ホプキンス大学のPaul Rothman氏からアカデミアに起業家精神を根付かせるための取り組みについて、スポンサーのCooley法律事務所のJosh Seidenfeld氏とEYのPhil Howard氏から米国で起業するための法務・財務について、CruxioのRob Wishnowsky氏から効果的なコミュニケーション等について、講演が行われました。
イベント終了後にはネットワーキングレセプションが開催され、参加者が交流を深め、情報交換を行う場が設けられました。
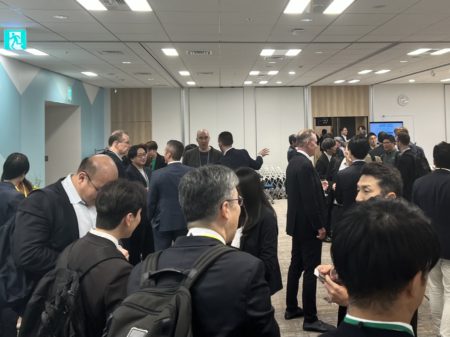
ネットワーキングレセプション
Science2Startup Japan Final Symposium 2024は、日本のアカデミア発のライフサイエンス技術シーズを医薬品産業に応用するための革新的なステップとなりました。
UTECとしても、S2S Japanを通じて、日本の研究者とグローバルパートナーが共に未来を創出する場を提供することで、日本のライフサイエンス分野が国際社会で飛躍する一助となれるよう、今後も取り組んでまいります。